

“中小企業診断士”とは経営コンサルタントの唯一の国家資格(経済産業大臣登録)です。
名前の通り、中小企業の経営に関する診断・助言を行う専門家のことです。

そんな中小企業診断士について、「どんな資格なのか?」を徹底解説していきます!
どんな人が受けるの?
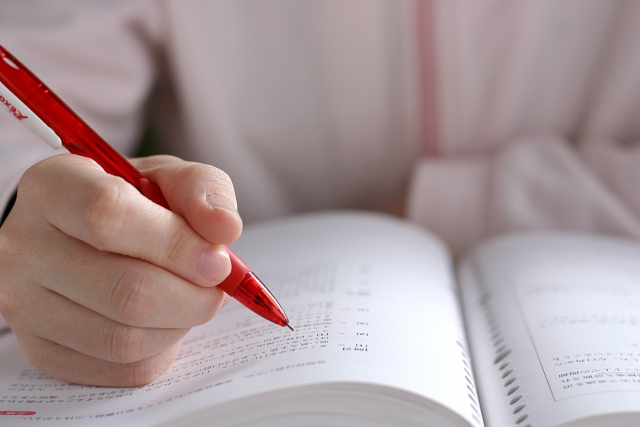
中小企業診断士や経営コンサルタントとして独立を目指したい人や、スキルアップをして企業内でもっと活躍したい会社員の方など、幅広い層が受験しています。
ビジネスに関する基礎的な知識が求められる資格試験のため、多くのビジネスパーソンにとってプラスに働くことが、この資格の人気に火が付いている理由の1つと言えます。

それでは、実際にどんな人が中小企業診断士に挑戦しているのか、中小企業診断士協会のホームページに掲載されている「2018年度(平成30年度)中小企業診断士第1次試験に関する統計資料」(PDF)から探っていきましょう。
年齢別にみる特徴
まずは年齢別の申込者数と構成比から見ていきましょう。
下記の表が2018年度の第1次試験を受験した方の年齢構成です。
| 申込者数 | 構成比 | |
| 20歳未満 | 96人 | 0.5% |
| 20~29歳 | 2,999人 | 14.9% |
| 30~39歳 | 6,376人 | 31.7% |
| 40~49歳 | 6,057人 | 30.1% |
| 50~59歳 | 3,526人 | 17.5% |
| 60~69歳 | 949人 | 4.7% |
| 70歳以上 | 113人 | 0.6% |
| 合計 | 20,116人 | 100.0% |


ちなみに2018年度(平成30年度)1次試験合格者の最年長は78歳、最年少は19歳となっています。
男女別にみる特徴
次に、男女別の申込者数と構成比を見てみましょう。
| 申込者数 | 構成比 | |
| 男性 | 18,144人 | 90.2% |
| 女性 | 1,972人 | 9.8% |
| 合計 | 20,118人 | 100.0% |


中小企業診断士の試験内容
中小企業診断士を取得するまでの大まかな流れは、
- 「第1次試験」・・・7科目の筆記試験
- 「第2次試験(筆記試験)」・・・4つの事例を題材にした筆記試験
- 「第2次試験(口述試験)」・・・第2次試験(筆記試験)の事例をもとにした面接試験
- 「実務補習」or「診断実務従事」(15日間以上)
上記3回の試験に合格した後、
以上の過程を経て、晴れて“中小企業診断士”の資格を手にいれることができます。

つまり“誰でも挑戦することができる資格試験”なのです!
第1次試験
中小企業診断士試験の第1次試験は毎年8月上旬の週末(土日)、2日間に分けて行われます。
試験科目は7科目あり、マークシートによる択一方式で実施されます。
<1日目>
A 経済学・経済政策
B 財務・会計
C 企業経営理論
D 運営管理(オペレーション・マネジメント)
<2日目>
E 経営法務
F 経営情報システム
G 中小企業経営・中小企業政策
ちなみに、中小企業診断士試験の第1次試験には『科目合格制度』がとられています。
第1次試験の合格基準は通常、「総得点の60%以上で、かつ40%未満の科目がないこと」とされていますが、必ずしも1回の試験で7科目すべてに合格する必要はありません。
合格した科目(得点が60%以上だった科目)については2年間、その科目を免除することが可能となります。


なお、第1次試験の合格はその年度と翌年度の2年間有効です。その年度の第2次試験で不合格となってしまっても、翌年度は第1次試験を受験せず、第2次試験からスタートすることができます。
第2次試験(筆記試験)
第2次試験(筆記試験)では、「中小企業の診断および助言に関する実務の事例」について、筆記(短答式または論文式)の方法により実施されます。
下記テーマの4つの事例が出題され、各事例80分ずつで解いていきます。
<中小企業の診断及び助言に関する実務の事例>
- 「組織(人事を含む)を中心とした経営の戦略及び管理に関する事例」
- 「マーケティング・流通を中心とした経営の戦略及び管理に関する事例」
- 「生産・技術を中心とした経営の戦略及び管理に関する事例」
- 「財務・会計を中心とした経営の戦略及び管理に関する事例」
こちらも第1次試験と同様、合格基準は「総得点の60%以上で、かつ40%未満の科目がないこと」とされています。
この第2次試験(筆記試験)に合格すると、次の第2次試験(口述試験)の受験資格を得ることができます。
第2次試験(口述試験)
第2次試験(筆記試験)に合格した人を対象に、口述の方法による試験が実施されます。
具体的には、中小企業の診断及び助言に関する能力について、筆記試験の事例などをもとに、個人ごとに面接を実施します。


実務補習or診断実務従事
第2次試験に合格した後、3年以内に実務補習を15日以上受けるか、診断実務に15日以上従事することにより、中小企業診断士としての登録を行うことができることになっています。
普段、仕事で診断業務を行っていない人は、「実務補習」を受ける流れになります。
実務補習は中小企業診断協会が実施していて、15日コースと5日コースが用意されています。
3年以内に15日コースを1回受けるか、5日コースを3回受けることで、登録の要件を満たすことになります。
普段から仕事で経営コンサルタントなどを行っている人は、実務補習を受けずに、15日以上の「診断実務」に従事すれば登録の要件を満たすことができます。
中小企業診断士の難易度・合格率は?
ここで中小企業診断士試験の合格率をみてみましょう。
第1次試験の合格率の推移は以下のとおりです。
<第1次試験 合格率>
| 2016年度(平成28年度) | 17.7% |
| 2017年度(平成29年度) | 21.7% |
| 2018年度(平成30年度) | 23.5% |
第2次試験の合格率の推移は以下のとおりです。
<第2次試験 合格率>
| 2016年度(平成28年度) | 19.2% |
| 2017年度(平成29年度) | 19.4% |
| 2018年度(平成30年度) | 18.8% |
年度によって多少の違いはありますが、第1次試験・第2次試験ともに合格率は20%前後になることがほとんどです。
ちなみに「第2次試験の合格者数」を「第1次試験の受験者数」で割った最終合格率は毎年4~5%程度となっています。
単純計算だと100人に4,5人しか合格できないということです。
また、上記で説明した通り、中小企業診断士試験は勉強範囲が広くボリュームも多いため、一般的には難関資格とされています。
しかし、難しい試験だからこそ、中小企業診断士は希少価値があり、周りからの評価も高いのです。
取得までの道のりは長く険しいですが、その分、合格できれば見返りも大きい資格です。
このサイトで勉強法などを紹介していますので、「挑戦しようかな~?」と少しでも考えている方は、是非チャレンジしてみてください!






