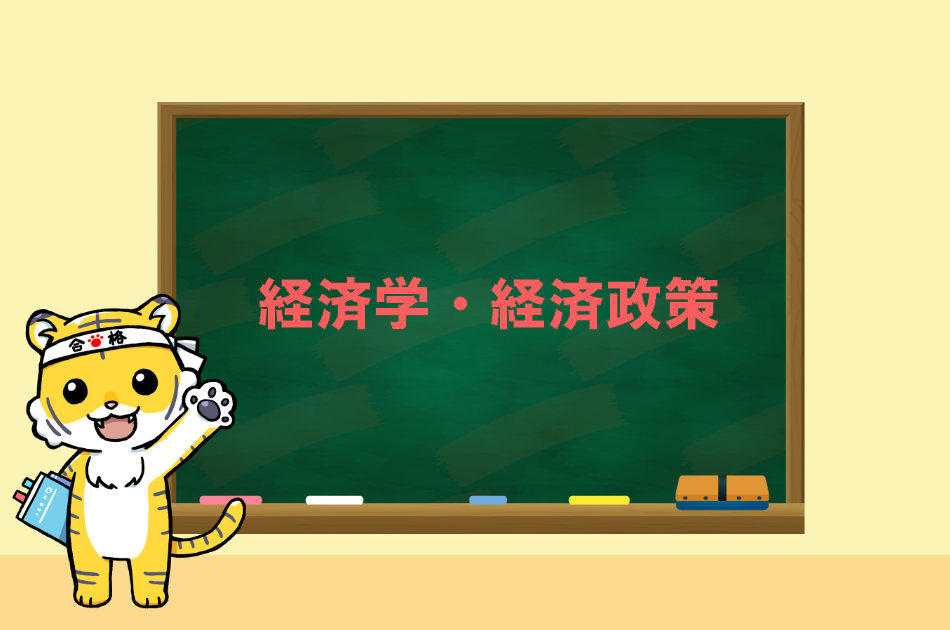

金融政策とは?
金融政策とは、中央銀行(日本だと日本銀行)が、物価の安定を図り国民経済の発展を助けるために行う、金融面からの経済政策のことです。

金融政策には主に「公定歩合操作」、「公開市場操作」、「法定準備率操作」の3つがあります。
公定歩合操作
中央銀行が民間銀行に資金を貸す際の金利である公定歩合を変化させて、民間銀行が中央銀行から借りる資金を調整する政策のことです。

公開市場操作(オペレーション)
中央銀行が国債や手形などの売買を通じて、マネタリーベースの量を変更することで、マネーストックを操作する政策のことです。
公開市場操作(オペレーション)は大きく分けて、中央銀行が資金の貸付けや国債の買入れなど、金融市場に資金を供給するオペレーション(買いオペ)と、中央銀行が振り出す手形の売出しや、保有している国債の買戻条件付売却など、金融市場から資金を吸収するオペレーション(売りオペ)があります。
預金準備率操作
中央銀行は金融機関の預金などを、ある一定の割合で中央銀行に預け入れさせています。その預け入れの割合(預金準備率、法定準備率)を調整することで、金融の引き締め、緩和を行う政策です。



